【設計製図試験対策】2024年の本試験を分析
一級建築士の学科試験対策で過去問での繰り返し学習がとても重要であるように、設計製図試験も同様に本試験課題を対策・分析が受験対策の王道です。
今回は2024年の設計製図試験を試験当日を振り返りながら私なりに分析していきます。
まず製図試験の課題が、例年通り学科試験直前のタイミングで発表されました。
課題名「大学」
留意事項
- 敷地の周辺環境に配慮して計画する。
- バリアフリー、省エネルギー、二酸化炭素排出量削減、セキュリティ等に配慮して計画する。
- 要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。
- 大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。
- 建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。
- 構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を計画する。
- 空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。
といった内容です。
課題名が「大学」だけのシンプルさに、いろんなことが想定されるとのことで、資格学校曰く「対策に苦労する」とのことでした。
それでは本題です。
課題文を分析
それでは早速、設計条件から。
設計条件から読み取る
課題文より、
ある都市の市街地の駅前にあり、基礎免震構造を採用した、大学の建築学科棟を計画する。なお、実験棟等の施設については、郊外のキャンパスにあるものとする。
基礎免震構造を採用とのことですが、課題発表時の留意事項「大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする」と記載があったので、資格学校の課題で何度か基礎免震構造で計画することを学習していましたので、対策済みです。

平成27年の本試験「デイサービス付き高齢者向け集合住宅」では、基礎免震構造を採用した建築物、と指定されていました。
計画にあたっては次のことが求められています。
- 建築を学ぶ上うえで、参考(教材)となるような建築物
- 学生や教職員の多様性への配慮及びユニバーサルデザイン
- 大地震等の自然災害が発生した際、発災から72時間程度まで学生・教職員の帰宅困難者の一時滞在に配慮した計画
冒頭からこの文言を目にすることになり、本試験中の私の気持ちとしては
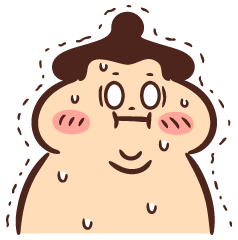
教材となるような建築物って・・・なに?
と、パニック状態。
ここで計画の要点等(記述)をチラ見してみると、
この建築物が学生にとって建築を学ぶうえで、参考となるような工夫(建築物の教材化)
序盤でここを深く考えてしまうと時間が足りなくなってしまいそうなので、エスキス時点ではいつも通り計画することにします。
また自然災害時の帰宅困難者の一時滞在に配慮とのことから、北側駅ビル・西側駅前広場にアクセスできる動線を考慮する必要がありそうです。
敷地及び周辺条件から読み取るポイント
敷地条件は「東西48m×南北35m」
- 東側:幅員6mの道路を挟んで店舗付き集合住宅
- 西側:駅前広場80m(道路法上の道路)&駅前ロータリー(バス乗場)、その奥に6階建て商業施設
- 南側:5階建て商業施設 ※商業施設の南側は歩道付き幅員16m道路
- 北側:自由通路に面して駅ビル(5階建て商業施設)

まとめると、
東側は幅員6m道路に接道・北側は駅ビル・西側は駅前広場・南側は商業施設です。
用途地域は近隣商業地域で準防火地域に指定されていて、建蔽率は80%(所定の加算を含む。)容積率の限度は400%歩道の切り開きは不可。
その他、積雪考慮なし・地盤良好・水害危険なし。このあたりの表現は例年通りです。
- 東側道路からのアクセス→駐車場及びエントランス入口
- 駅前広場側からのアクセス(駅・バス)→西側にもエントランスがあった方が良いかも(※必須ではない)
それと注視したいのが、敷地条件の表記です。
北側は自由通路で、境界線部分には「隣地境界線」の表記が。それと西側駅前広場80m側の表記は「道路境界線」
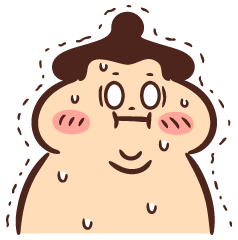
自由通路って、、、道路?
普段は気にもしないようなことが、なぜか試験の時は、全部が怪しく感じて、パニックになってしまいます。
高さ制限では、道路境界線と隣地境界線とでは検討する内容が変わってきますので要注意です。
構造・階数・要求室の読み取り
- 階数自由(地階は設けない)
- 構造種別自由
- 基礎免震構造
- 「建築物移動等円滑化基準」を満たすとともに、ユニバーサルデザインとすることが求められている

参考までに、、
2022年(令和4年)の本試験課題「事務所ビル」も階数指定がありませんでした。
構造種別は例年通り「自由」となっていますが、RC造で計画するのがベターですね。
多数の利用のある建築物に求められる性能から、遮音性・気密性・振動性に優れているため。
無柱空間を構成する架構との一体性を持たせるため、PC梁の併用を採用
災害時の避難場所としての役割もあることから、耐震性・耐火性に優れた構造である
建築物移動円滑化基準については、法規制のところで詳しく解説します。
要求室を読み取ります。
- 主に建築学科の学部3年生(定員80人)、4年生(定員80人)及び大学院生(定員80人)の総数240人の学生が使用する。(学部1年生及び2年生は郊外のキャンパスを利用)
- 建築学科の教員の人数は18人であり、研究室は18室以上必要である。
| 要求室 | 補足 | 要求面積 |
|---|---|---|
| 製図室 | 基準階の各階 | 計700m2以上 |
| 研究室 | 基準階の各階、合計18室以上 | 50m2/室以上 (計900m2以上) |
| 会議室 | 基準階の各階 | 適宜 |
| ラウンジ | 基準階の各階 | 適宜 |
| ゴミ保管庫 | ・基準階の各階 ・1階にゴミを搬出するためのスペース確保 | 適宜 |
| 講堂 | ・学生3学生・4年生・大学院生の講義や学内のイベント利用 ・段床形式で固定席300席 ・控室 | 適宜 |
| 教室A・B | 学生80人の講義が可能な2室 | 適宜 |
| 教室C・D | 学生50人の講義が可能な2室 | 適宜 |
| 図書室 | ・建築関連の雑誌・書籍が閲覧できる室 ・書架、閲覧席 | 100m2以上 |
| カフェ | 50m2以上 | |
| 事務室 | ・事務スペース ・受付 | 50m2以上 |
| 防災倉庫 | 適宜 | |
| 受水槽室 | ・受水槽及び吸水ポンプ ・一時滞在を考慮した受水槽を設ける | 50m2以上 |
| 消火ポンプ室 | 屋内消火栓用 | 適宜 |
| 電気設備 | キュービクルを屋上設置 | |
| 空調室外機、エレベーター、PS、DS、EPS等を適切に。 | ||
| 太陽光パネルを屋上設置 | ||
| その他適宜 | 施設管理・授業運営に必要な室等を適切に設ける |

適宜計画する室をピックアップすると・・・
印刷室(コピー室)・教材をストックする室・更衣室・職員用トイレ・医務室・守衛室などが挙げられますね。
ゾーニングとしては、
管理・サービス部門
- 事務室
- 防災備蓄倉庫
- 受水槽室
- 消火ポンプ室
- ゴミ保管庫
- 守衛室(任意)
- 職員更衣室(任意)
- 職員用トイレ(任意)
その他が学生利用になります。

例年は
- 共用部門
- 管理+サービス部門
- その年の課題の部門
という構成が多いですね。
50m2以上・100m2以上という要求室が多いので、スパン割りは短辺7m×長辺7mのグリッドよりも、どちらか一辺が8mの8m×7mのスパン割りが計画しやすそうですね。
その他施設等
建物の配置計画に影響する駐車スペース。その条件を確認します。
- 駐車場は、車椅子使用者用として1台分のスペースを設ける。なお、建築物内に設けてもよい。
- 屋上庭園は、3階床レベル(2階の屋上)に、面積を50m2以上(屋根や庇となる部分は除く)確保し、3階のラウンジとの出入り口については、段差のない仕様とする。
周辺環境に配慮した上で、植栽、通路等を設ける。
駐車場の寸法は、
- サービス用駐車場→2.5m×5m
- 車椅子使用者用駐車場→3.5m×5m
資格学校では「串刺し駐車はNG」と言われていますが、標準解答例では串刺し駐車で計画されています。
法規制のチェック|法の抵触はランクⅣ(失格)?
大手資格学校では法に抵触するミスは一発アウトと習います。

違反建築物を合格とできるわけがないですね・・・考えてみたら納得。
注意すべき法規制がこちら。
- 高さ制限(道路高さ制限・隣地高さ制限)
- 採光
- 防火区画
- 2方向避難
- 歩行距離(重複距離)
- 延焼ライン
- 非常用の侵入口
- 敷地内通路
- バリアフリー
この中で、今回の課題である近隣商業地域に関連する法規制をピックアップして詳細を見てみます。
近隣商業地域に関連する法規制のチェック
用途地域によって異なる影響を受けるのが「高さ制限」と「採光」です。
近隣商業地域の高さ制限
用途地域によって変わるのが斜線勾配です。
- 道路斜線勾配=1.5A
A:前面道路の反対側境界線までの水平距離に建物が後退した場合その距離の2倍を加える - 隣地斜線制限=31m+2.5l
※「l」=隣地境界線までの水平距離の2倍
※住居系は20m+1.25l - 北側斜線制限の検討は不要(低層住居・中高層住居地域のみ)
道路斜線制限は無制限にかかるわけではなく、適用距離が決まっています。
| 用途地域 | ||
| 住居系 | 容積率≦200% | 20m |
| 200%<容積率≦300% | 25m | |
| 300%<容積率≦400% | 30m | |
| 400%<容積率 | 35m | |
| 商業系 | 容積率≦400% | 20m |
| 400%<容積率≦600% | 25m |
建築物を道路境界線よりセットバックして建築する場合、道路斜線制限の緩和規定が適用されるが、門や塀等までもセットしなければ、この緩和規定が適用されないのは現実的ではないので、次に掲げる建築物の部分及び門・塀は除外される。
- 建築物の部分で高さが1.2m以下のもの
- 物置等で次の条件を全て満足したもの(後述)
- ポーチ等で次の条件を全て満足したもの(後述)
- 道路に沿って設けられる高さが2m以下の門や塀。ただし、高さが1.2mを超えるものは、その超える部分は網状等であること
- 隣地境界線に沿って設けられる門や塀
②の条件
- 前面道路の中心からの軒の高さが2.3m以下
- 床面積の合計が5m2以内
- 間口が道路と敷地が接する長さの1/5以下
- 道路境界線から1m以上離れていること
③の条件
- 前面道路の中心からの高さが5m以下
- ポーチの間口が道路と敷地が接する長さの1/5以下
- 道路境界線から1m以上離れていること
近隣商業地域の採光
採光補正係数=10×d/hー1(商業系)
※住居系の採光補正係数=6×d/hー1.4











